
目次
- 就活スケジュール
- 就職活動 インターンシップ
- 集団面接のコツは?
- 合同企業説明会 参加のメリットとデメリット
- OB・OG訪問の注意点
- 業界別内定率を上げる証明写真
- 就活の面接で真実と違う話をした事はある?
- 就職先はどこが良いか?上手な優先順位の付け方
- 新卒時の就職先は?
- 激化する就活戦線、エントリーした企業の数
- グループディスカッションの役割毎の特徴
- 就活中に気を付けるべき身嗜みのポイント
- 就活生の誰もが抱く就活スタート時の悩み解消法
- インターンシップはいつから?
- まとめ
-
就活スケジュール
3月は幅広くエントリー
大半の企業は3月上旬から採用情報を公開し、エントリーシートの受付が始まり、就活生は5月末までに30社前後の企業にエントリーを行っているようです。エントリー数が多ければ良いというわけではありませんが、幅広くから選べるという環境で企業の選考を経験する機会を得られ、本命の企業選考に余裕を持てます。視野を広げるという意味でも様々な企業にエントリーを行う意識が大事です。
外資系企業やIT系、中堅や中小企業などでは早い時期から選考や面接を行って、内定や内々定を出している所もあります。
選考開始時期や内定(含む内々定)出しを開始する時期については6月以前に予定する企業が増えています。早期に採用選考を行う企業に応募する学生も年々増加傾向です。
希望先の企業の動向は早目に確認することをお勧めします -
就職活動 インターンシップ
約七割の学生が平均三社のインターンシップに参加
毎年インターンシップが開かれ参加者は年々増加しています。
参加経験のある学生の平均参加社数は3.0社で、積極的にインターンシップに参加している事が窺えます。インターンシップに参加する目的を経年で比較しますと、「特定の企業の事をよく知る為」、「就職活動に有利だと考えた」と言った理由が増加しており、学生の中では、かなりの目的意識をもってインターンシップに参加しており、早くから自分のキャリアをある程度見定めて活動していると見られます。
インターンシップに参加する目的
・特定の企業の事を良く知る為
・志望企業や志望業界での実務を経験する為
・仕事に対する自分の適性を知る為
・自分が何をやりたいかを見つめる為
・就職活動に有利だと考えた為
・社会勉強の為
以上六つが参加目的とした上位に入る内容となります。応募時に重視しているのは「企業名」や「期間」が増加傾向
文系を中心に応募数が増加しています。
応募時に重視する事の上位、「業種」「職種」「プログラム内容」は例年変わりませんが、「期間」「企業名」は、最近増加しており、企業名を優先して短期間のプログラムに多く参加する傾向と言えます。参加しやすさで短期間を希望する割合が増加
企業の参加機関は「一週間以上」の割合は約三割でした。
学生が考える、参加しやすいと思うインターンシップ期間は「一日」で、文系学生を中心に年々増加しています。実際に参加した中で、最も印象に残った企業のインターンシップ期間を見ると、「一日」が48.6%で最も多く、「一週間以上」が30.2%と、参加しやすさと比較して、期間の長い方が印象に残りやすいといえます。
一週間以上のプログラムを選択した理系学生は37.0%であるのに対し、文系の学生は25.6%と開きがあります。最も興味を持つプログラム内容
実際の現場での仕事体験 36.5%
実際の仕事のシミュレーション体験 16%
会社見学、工場見学、職場見学 14.6%
グループワーク 12%
若手社員との交流会 9.7%
その他 12%
インターンシップの内容で最も興味を持たれたのは、「実際の現場での仕事体験」36.5%がトップでした。リアルな現場体験が望まれているようです。話を聞いてみたいと思う社会人暦
入社1~2年目 62%
入社3~5年 51%
年次の関係なく希望する職種に関係する人 33%
入社6~10年 22%
入社11年以上 19%
経営者 11%
「若手社員との交流会」に興味を持つ割合が年々増加しています。これは、インターンシップに参加して話を聞いてみたいと思う社会人として、入社1~2年目が62%、3~5年が51%と多く選ばれている事からも伺えます。インターンシップに参加して聞いてみたい事
社内の人間関係や雰囲気 76.3%
具体的な仕事内容 67.7%
仕事のやりがい・満足感 52.6%
入社を決めた理由 52%
就活時の面接対策や選考対策 42.2%
残業・休日出勤の実 38.6%
入社前・後で会社に対する印象の変化 36%
有給休暇の利用状況 33.5%
会社の長所・短所 32.6%インターンシップに参加して良かった点
社員と会話する機会が多かった 49.8%
プログラム内容が理解しやすかった 46.2%
実際の業務を体験できた 32%
個々に対するフィードバックが十分だった 25.6%
インターンシップに参加して良かった点を見ると、「学生が選ぶインターンシップアワード」の選考基準と(社員の協力体制、独自性、指導性、効果性)等とも合致しているので、プログラムを検討する上で参考になると思われます。インターンシップに参加した時期、参加する時期
第一位 今年8月
第二位 今年9月
第三位 今年12月
第四位 来年2月
第五位 来年1月
すでに就活は夏休みから始まっている事が見受けられます。インターンシップに参加して自分自身に起こった変化
興味のある業界・企業・仕事内容の範囲が広がった 52%
自分に足りない能力を把握できた 50.3%
今まで知らなかった業界・企業・仕事内容に興味が出た 38.4%
自分で思っている以上に多様な選択がある事が分かった 26.7%
就職活動で自分の視野が広がった 22%
「興味のある業界・企業・仕事内容の範囲が広がった」の展望化が一位となりました。二位には「自分に足りない能力を把握できた」と自己理解となり、キャリア焦点化や人的ネットワークの認知、就労意欲よりも、展望化や自己理解のほうが強いと感じられます。インターンシップに参加した各企業から参加後の問合せ
一ヶ月に一回程度 46%
連絡を受けていない 41%
一ヶ月に二回程度 8.2%
一ヶ月に三回程度 3.3%
ほぼ毎週 1.5%
参加後の問合せ内容
次回の別インターンシップ 71%
インターンシップ参加者限定の採用選考案内 18%
参加したインターンシップに関連する課題 11.4%
会社訪問や工場見学等の案内 11%
OB・OGの紹介・訪問の案内 9.4%
3月以降の採用スケジュールの案内 6.8%
その他 11.5% -
集団面接のコツは?
個人面接や役員面接に進むには、集団面接で面接官から良い評価を得ることです。一人一人の持ち時間が少なく、初対面で顔を合わせた他の就活生と発言を比較されてしまう集団面接では、コミュニケーション能力の高い人が有利なのは否めません。しかし面接官から良い評価を得るために必要なのは、面白おかしい話をする事でも誰とでも仲良くすることでもありません。口下手な人でも集団面接を突破するためのコツはあるのです。
集団面接で求められている事
● 質問された内容を正確に理解できるか
● 伝えたい内容を簡潔に短く纏めて伝えられるか
を見ることです。内定を貰い就職した後は、同僚や上司、取引先等とコミュニケーションを取りながら仕事を進めます。最低限相手の言っていることを理解し、適切に返すことが出来なければそもそもの仕事になりません。「コミュニケーション能力」とは、「誰とでもすぐに仲良くなる会話力」でも「誰にでも好かれる性格」でもないのです。企業が求めるのは、「聞く力」、「伝える力」のコミュニケーション能力なのです。
口下手でも面接官からの質問を正しく理解し、短く分かり易く返答できれば、評価としては十分なのです。又、話す内容だけでなく集団面接中のほかの就活生が話している時の態度、姿勢、言葉遣いなどもチェックの対象です。一般常識が無い、基本的なマナーが無いなどと面接官に思われてしまうと。大きなマイナス評価になりかねません。目立つ事、沢山話す事は重要ではない。
集団面接ではとかく、「目立とう」「沢山話そう」と考えがちです。しかし集団面接で重要なのは、目だったり沢山話したりすることではないのです。企業側は「一緒に働きたい」「一緒に働いても大丈夫」を思う人を探しているので、就活の集団面接で目立つ為に、割り振られた時間より長く話そうとしたり、他の人が話しているのを遮って話したりするように人がいたら、一緒に働きたいと思われるでしょうか。
大切なのは、「面接官から聞かれた事に精一杯の答えを返す」事です。内容の無い話をダラダラする人より、思いを込め、短くても会話のキャッチボールが出来る人の方が評価してもらえます。聞かれた事に簡潔に返す。
集団面接では、就活生一人当たりの回答時間は短くなります。最初に行われる自己紹介や自己PRも「一分程度で」などと時間を指定されたりします。志望内容や趣味・特技について長々と語ることなど出来ません。聞かれた事について出来るだけ簡潔に答えましょう。
「短時間で」「相手に分かり易い表現」で「聞かれた事に対する回答」をする為には、高い国語力が求められます。「早く答えなければ」と焦って適当な返答をするよりも、一拍置いて考えてから簡潔な返答をする方が重要です。そうは言っても、何も準備していない状況で素早く簡潔に答えるのは困難です。良く聞かれる「学生時代に頑張った事」「入社後どういう仕事をしたいのか」などは事前に答えを考えて置けますが、決まりきった答えだとわざとらしさが出てしまうので、丸々答えを用意するのではなく、「こう聞かれた場合は、このキーワードで返答する」と言う感じに準備しておくと良いでしょう。
尚、「一分程度で」など回答時間を指定された場合は時間を守りましょう。多少の前後は許されますが、長々と話してしまうと上司の指示を守れない人間だと、判断されてしまいます。ハキハキとゆっくり、分かり易く話す事を心がける
集団面接に限らず、面接ではハキハキとゆっくり話すことを心がけましょう。集団面接で重要なのは、質問に対して短く分かり易く答える事ですが、人間の印象は話の内容だけでなく、態度や声などによっても左右されます。オドオドした態度や、ボソボソした発言をしていては、言いたい事は伝わりません。態度や、話し方しだいで本来持っている人間的な魅力まで下がってしまうのです。
集団面接では、複数の就活生が互いに比較されます。「他の就活生より自信を持ってはなしている」「聞き取りやすい」と感じてもらえば評価が上がる事でしょう。ESや細かな所作で差をつける
口下手な人にお勧めしたいのは、「発言以外の自己PR」を良くする事です。たとえば、ESの作り込みに会話力は必要ありません。面接官の気を引くような志望動機だったり、興味を持ってもらえるような趣味・特技が合ったりすればその分面接で優位に立てます。又、複数人が同時に並ぶ集団面接では、座っている時の姿勢や、立ち上がる際の動作、お辞儀の仕方等、細かな所作に気を使うと美しく見えて有利です。履歴書の添え状を付けたり、面接後にお礼のはがきやメールを送ったりと、口下手な人は会話以外のアピール方法を駆使してライバルに差をつけましょう。
-
合同企業説明会 参加のメリットとデメリット
就職活動が始まると、大手就職活動支援企業が主催する「合同企業説明会」に参加される人が多いと思います。沢山の企業から人事担当者が集まるイベントで、「フェア」、「エキスポ」、「ライブ」などと呼ばれる事もあります。
合同企業説明会は、個別の企業説明会とは異なり、メリットやデメリットがあります。それらを理解せずに参加すると、「結局何をしに行ったのか分からない」、「時間の無駄になった」という事にもなりかねません。
参加する意義を理解しておきましょう。メリット 1 興味が無い企業の話を聞く切っ掛けとなる。
個別の企業説明会は各企業が力を入れて行っていますが、わざわざ会社を訪問する個別企業説明会では、ある程度興味のある業界や企業の主催する物でなければ、殆どの就活生は参加しないという結果になります。
その一方で合同企業説明会では、150社以上が参加する大規模な物もあります。全く興味の無かった業界や企業が参加しているケースもあるでしょう。
大規模なイベントであれば、わずかの時間でブースに立ち寄り、気軽に人事担当者と話をする事も出来ます。それまで興味の無かった業界や、少ししか興味の無かった企業の話を聞いてみる事も可能です。
そういった多くの出会いの中には、「意外と自分に向いているかも?」、「この仕事案外面白そう」といった新たな発見があるかもしれません。
興味のある企業しか見ていない就活生より、色々と幅広く見ている就活生のほうが情報も多く集まるので、興味の無い企業にも目を向けると良いでしょう。メリット 3 企業の情報を効率よく集められる
合同企業説明会における企業毎の会社説明は、一つのブースにつき30分から1時間程度になります。開始から効率よく企業を回れば、1日で5社以上の説明を聞くことの十分可能です。
個別の企業説明会に参加するとなると、移動時間も含め、せいぜい一日に2社程度回れれば良い方ではないでしょうか。興味のある企業の説明を1日で沢山回れる合同企業説明会は、効率的といえますのでお勧めです。デメリット 1 個別の会社説明会程深い情報は出ない
個別の会社説明会では、通常1~2時間掛けて説明が行われます。場合によってはそれ以上の時間が掛かることもあります。合同説明会では、1社あたりの時間が限られていますので、余り込み入った詳しい情報は出してきません。企業に対するプラスイメージを持ってもらい、個別の企業説明会に誘導するのが目的です。その為すでに個別の企業説明会に参加している企業のブースを訪れると、既に知っている情報しか出てこないということも有ります。「物足りない」と思う人もいることでしょう。デメリット 2 「なんとなく」で行くと時間の無駄
興味の無い業界や企業にも目を向けるきっかけになるとは言え、全く就職する可能性の無い企業ばかり回っても意味がありません。しかも「なんとなく」、「友達に誘われた」などといった理由で参加すると、何も実りの無い無駄な時間になりますので気をつけましょう。
あらかじめパンフレット等で参加する企業に目星を付けておいて、効率的に回ると良いでしょう。先に興味のあるブースを絞っておけば、空いている順に回っても時間を無駄にしません。企業の雰囲気を感じ取る
合同企業説明会では、企業の採用担当者も一人だけと言う事は無くたいてい数人で参加しているので担当者同士の雰囲気から、ある程度企業の雰囲気も見えてくると思います。担当者に活気があり、自信と情熱を持って説明している企業は魅力的に見えます。企業の規模や説明の内容だけでなく、こういう点もチェックしておくと良いでしょう。企業側も就活生から面談されているみたいですが。
最近はSNSでアップされる機会いが多く、宣伝効果を狙っているのか合同説明会参加者にお土産を用意する企業も少なくありません。就職活動に活かせる情報を得られる上、お土産まで手に入るなんてお得ですね。合同企業説明会に参加する際は、目的意識をしっかり持ち、計画を立て、限られた就職活動の時間を有効に使いましょう。
-
OB・OG訪問の注意点
就職稼動を有利に進めたり、志望業界「矢企業に対する正しい知識を得たりと、情報収集が大切になります。そこで重要なのは、「OB訪問」です。OB(Old Boy)は学校の先輩をさす言葉です。(女性の場合はOG(Old Girl)になります。)
OB訪問は、仕事の内容を正しく理解し、企業の雰囲気を感じ取れる、貴重な機会です。より有意義なものにする為に、メリットと注意点を確認しましょう。
OB訪問とはなにか
OB訪問とは、自分の所属する大学等の卒業生のうち、自分が志望する業界や企業に就職している人の元を訪れる事です。学校の就職課やキャリアセンター、就職指導教官等に相談すれば、訪問先を紹介してもらえます。所属のゼミや研究室、サークル等の人脈を利用するのも良いでしょう。
志望する業界が共通する友人と、手分けして訪問先を探すことも出来るでしょう。
OB訪問は自分で訪問先を探す必要がある為、就活生の全てが経験する訳ではありません。就活生全体の四割程がOB訪問を行っているといわれています。OB訪問のメリット
OB訪問には大きく分けて、次のようなメリットがあります。正式な企業説明会との違いを把握して置く事でより充実した情報収集が出来ます。・メリット 1 実際の情報が得られる
会社紹介のパンフレットやホームページ等は取引先、顧客の目に触れても問題が無いように作られているので、得られる情報には限りがあります。しかし実際に働いている人の話を聞けば、社風や実際の勤務状況など、生きた情報が得られます。・メリット 3 非公開情報を聞ける場合も
採用担当者は自企業の悪い点は基本的に口にしません。OB訪問では業務の中で苦労している点や、ライバル企業との差異など、企業説明会では聞きにくい情報を聞ける場合もあります。又、場合によっては非公開情報等を聞ける事も有るかもしれません。OB訪問を有意義な時間にするコツ
実際に企業で働いている社会人に連絡を取り、自分の為に時間を割いてもらうのはなかなかハードルの高い作業です。せっかく作った自分と相手の時間を無駄にしないように、OB訪問を行う前に自己PRや志望動機、学生時代に頑張った事等、話す内容を用意します。
OB訪問では、それらが通用するかどうか、内定を貰えるかという点を意識して情報を聞くのがお勧めです。たとえば、自己PRでアピールする能力について、「業務の中でこのような能力は必要とされますか?」「業務の中で最も必要な能力は?」「こういう自己PRを考えていますが、これは評価の対象となりますか?」などです。
具体的に文章等で用意しておけば、「この自己PRは業界に必要とされる能力とずれているな」「志望動機にこれもプラスできるな」などと、聞いたときにプラスの内容を答えようとしてくれます。何も用意せずに話をして、後日それを参考に対策しようと思っても、書き留めていないとどこか的外れになってしまいがちです。大切なのは事前に用意をして臨む事です。又、他に知りたい情報があればそれも纏めておくと良いでしょう。OB・OGの探し方
OB訪問について、訪問先を探すための具体的なルールはありません。訪問先を探す時の利用先は、なんといっても学校の就職課、キャリアセンターの紹介になります。連絡先を教えてもらい、電話やメールで趣旨を説明しアポイントを取る様にしましょう。
研究室やゼミの先輩であれば、ピンポイントで興味のある業界に繋がりやすいというケースもあります、訪問先の先輩に失礼の無い様に接すれば、そこからさらに業界の知り合いを紹介してもらえたりするケースもあります。
就活フェアで名刺をもらった人に連絡して、OB訪問のアポイントを取る人もいます。就活生の友人と一緒にお願いすれば、比較的時間を作ってもらい易かったりしますので、情報交換のためにも友人関係を保つ様に心がけましょう。こちら、成功すればポイントも大きいでしょう。
入社して間もない人は、新入社員に近い立場で情報や意見をくれますし、ある程度キャリアを積んだ人からは、企業の中で一定のポジションを築いているので、採用担当者に近い意見をもらえる可能性が高いと言えます。年齢の離れた人にアポイントを取るのは、ハードルが高いですが、訪問を重ねて経験を積み、そういった訪問先も視野に入るでしょう。OB訪問の注意点
OB訪問は全ての就活生が行う訳ではないので、上手に活用すれば他の就活生に差をつけることにも繋がります。しかし、訪問を受けるOB・OGにとっては、メリットはありません。
忙しい業務の合間を縫って時間を割いてもらうのですから、失礼の無い様にマナーに注意する事は勿論、「ダラダラ話さず簡潔に伝える」「結論を先に言う」などを心がけましょう。
アポイントを取る時間は、基本的に平日のランチタイムに合わせる様にします。何より相手の都合を優先し、別の時間を指定された場合はそれに従います。飲食代等は自分で払うのが当然ですが、相手から出してくれる場合はあまり固辞せず、キチンとお礼を言ってありがたくご馳走になりましょう。
別れ際にお礼を言うことは当然として、メールでその日の内に再度お礼を送りましょう。社会人と接する事に慣れると言う意味でも、OB訪問は有意義といえるでしょう。 -
業界別内定率を上げる証明写真の撮り方
業界別内定率を上げる証明写真の撮り方
東京では、池袋、新宿、板橋、江戸川、入間
埼玉では、大宮、浦和、川口、川越、深谷
大阪では、難波、淀屋橋、東大阪
名古屋、金沢、新潟、広島、福島、山形、秋田など全国にある就活写真専門スタジオフォプロ!!
https://www.phopro.jp/studio/
全国の就活生が選ぶ!
人気の証明写真スタジオNO.1
理想の写真が取れる写真スタジオNO.1
理想のヘアメイクを行う写真スタジオNO.1
写真スタジオ御客様利用満足度NO.1
4冠に選ばれました!!
-
就活の面接で真実と違う話をした事はある?
就職活動では、大勢の採用希望者に交じって、自分が一番であるというアピールをしなければなりません。面接担当者から質問され、過去の経験を振り返りながらアピールするものです。しかし過去。に、就職活動でアピールできるような実績やエピソードが余り無いと悩んでしまうものです。面接担当者に披露できるエピソードが無いと話を盛ったり、つい噓をついたりしたくなるものです。実際の面接の場で「真実ではないエピソードを語った事がある」と言う方は、どれくらいいるのでしょうか?就職活動中に面接を受けた方を対象に、アンケートをとってみました。どのような結果だったでしょう。
アンケート
就活の面接で真実とは違う話をした事はありますか?
〇 無い 57%
〇 真実を誇張・矮小化して話した事がある 32%
〇 真実とは全く違う事を話した事がある 11%1位 無い 57%
>真実ではない事を話してしまうと、その後が上手く話せなくなりそうだと思ったので、真実だけを話すようにした。 [静岡県/30代女性]>事実だけ話すようにした。事実と違う事を話しても後々偽った事がわかると信用を無くしてしまうので。 [千葉県/40代女性]
>全く経験していない事は話したくても話せません。 [東京都/30代男性]
最も回答数が多かったのは、「無い」で、57%でした。「真実のみを話した」と言う方が多く、嘘をついてしまう事で面接担当者に興味を持たれ、深追いされてボロが出てしまう事のリスクを避けた、という考え方が多かったようです。又、嘘をついた事がバレてしまうと、面接の評価は非常に悪くなってしまいます。面接担当者の信用も無くす事になり以降の質問に本当の事を言っても信じてもらえなくなる可能性は高いです。
2位 真実を誇張・矮小化して話したことがある 32%
>全くの嘘は後でバレるのが心配ですが、自己アピールする為に多少の誇張は必要だと思ったので。 [愛知県/30代女性]>面接でのコツやポイントなど勉強して、良い印象になるように回答をしたと思います。 [東京都/代女性]
>真実をある程度誇張したりするのは、自己アピールする上で必要だと思います。[神奈川県/30代男性]
二番目に回答数が多かったのは、「真実を誇張、又は矮小化して話した事がある」で32%でした。一番目の選択率からもわかるように、全くの嘘をさも事実でであったかのように自己PRするのはリスクが高いし、何より心苦しいと思う方が非常に多い傾向です。しかし誰でも多少は自分を良く見せたいと思い、多少誇張した自己PRをしたり、事実の中に適度に嘘を混ぜ込んだりして話す方もいます。事実に基づいて誇張表現すればボロが出にくいという事でしょうか。
3位 真実とは全く違う事を話した事がある 11%
>ただのバイトだったのにバイトリーダーをしていたと話した事がある。[兵庫県/30代女性]>かなり大げさに経験したことを話した事がありました。[愛知県/30代女性]
>学生時代は遊んでばかりだったので、面接で話せるネタを捏造した。[北海道20代男性]
最も回答数が少なかったのは、「真実とは全く違う事を話した事がある」で11%でした。数は少ないものの、「バレない範囲で嘘のエピソードを語っていた」と言う方もいるようです。確かに証拠などは無いため大げさな表現や事実と違う事を言っても、面接担当者は事実確認するすべがありません。ただ、ある程度矛盾の無いエピソードと深追いされた時の対処法等をなど練っておかないと困難な事態になる恐れがあります。
まとめ
実際に面接を受けた方の半数以上は、嘘をつかず真実を話しているようです。「ちょっと誇張(矮小)したけど大体真実を話した」と言う方を加えると、9割近い方々が就職活動の場では真実ベース(多少脚色しても)で自己PRをしているようです。就職活動においては、面接官に与えるインパクトは重要です。「おっ!」と思わせるような実績や、エピソードを語ることが出来れば、印象に残る上、採用するメリット等を十分に伝える事ができるでしょう。
その為にも、多少誇張したり脚色を加えたりする事は、必ずしもNGであるとは言えないでしょう。しかしあまりにも真実とかけ離れた誇張や脚色をしてしまうと、取り繕う事が難しくなってしまいます。嘘をついたり、壮大なエピソードを語ったりして注目を集めたとしても、その事についてさらに深く踏み込んだ質問をしてくる事もあるのです。嘘のエピソードを更に嘘で塗り固めようとしても、面接の場では緊張が伴います。予想外の質問をされてしまうと頭が真っ白になってしまう事も良くあります。そんな状態で嘘を重ねてもどこかで矛盾や綻びが生じてしまうでしょう。
面接官は多くの採用希望者の面接をし、経験豊富です。どこかで嘘と見抜かれてしまう恐れがあります。もちろん面接中に嘘であると指摘はされないかもしれませんが、評価はかなり下がってしまうでしょう。そのような状態では内定を得るのはかなり厳しいでしょう。もし今後就職活動で面接に臨む場合は、「真実を話す」を原則にした方がお薦めと言えます。また、誇張や脚色を加える場合でも大げさにせず、ボロが出ないよう、多少突っ込まれても対処できる程度に留めておいた方が良いといえるでしょう。
-
就職先はどこが良いか?上手な優先順位の付け方
就職先を考えるに当たって、仕事の内容に対する好き嫌いや遣り甲斐、会社やその業界の将来性、福利厚生、給与、休日等の待遇等、様々な要素があります。
「この職種は好きだけど、休みが取りづらい」「人に喜ばれ遣り甲斐があるが、将来性が微妙・・」など仕事は一長一短があります。全ての条件を満たす企業は滅多にありません。
人によりどの条件を優先するかは異なりますので、どの程度の水準で満足するかという基準も当然違ってきます。自分に合った就職先を選ぶ為に波動優先順位を付けると良いのでしょうか。全てが希望通りの企業から内定をもらえるとは限りません
自分が重視する条件を全て満たす企業は、そう滅多には出会えません。たとえ希望通りの企業を見つけても、そういった企業は非常に競争率も高く、内定をもらえる可能性は非常に低いと言えるでしょう。
希望通りの企業が見つからない場合や見つかっても採用に至らない場合には、優先順位に従って就職先を選ぶ必要が出てきます。条件ごとに基準を設けておき、優先順位の低い項目についてはある程度妥協することも考えましょう。
その際、優先順位が高く自分の中で譲れない項目は、出来る限り妥協しないで下さい。「どこでもいいから就職しよう」などと考え始めると、ブラック企業などに入ってひどい労働環境を強いられたり、「こんなはずではなかった」と後悔しながら働く羽目になったりするかもしれません。選択の軸にすべき条件 1 給料・福利厚生
新卒で就職する際は、それまでの学生時代のアルバイト等に比べるとグッと収入が増えることになります。その為、給料について具体的な基準を持っている人は少ないかもしれません。しかし就職して何年か経つと多くの人が結婚を考えたり、転職や独立して起業する事を考えたりと、将来を見据えた動きを始めます。
「家庭を持ち子供を養う」「独立に必要な資金を用意する」などと言う具体的なプランを立てるのも、ある程度の収入を得て初めて実現可能と言えます。又、社会人にとって、給与は自分の働きに対する評価とも考えられるものです。あまりに給与が低いと、自分の価値が低く感じられて心が折れてしまう原因となる事もあります。
反対に給与の高さだけを優先すると、きつい仕事で休みも殆ど取れないブラック系企業を選んでしまう可能性もありますので、注意してください。
「好きな仕事だから安い給料でもいい」などと思わず、どの程度の給与が有ればきちんと生活が成り立つのかを考えてみましょう。選択の軸にすべき条件 2 労働環境・勤務時間
学生時代にアルバイトを頑張った経験のある人が陥りやすいのが、労働時間に対する考え方の甘さです。
若い内は体力があって、家族と過ごす時間もそれ程必要性を感じないため、あまり寝ずに働いてもそれ程苦になりません。しかし就職して数年も経てば年齢も上がり体力も相応に落ちてきます。結婚して家庭を持つと、私生活に割ける時間が少ない事が更に苦痛に感じるようになる事もあります。
「人の役に立つやりがいのある仕事したい」「どうしてもこの職種で働きたい」といった人は、勤務時間や休日の部分である程度妥協が必要かもしれません。但し年齢が上がり家庭を持っても持続可能な環境であるか、問い雨天はよく検討しましょう。選択の軸にすべき条件 3 遣り甲斐・将来性
労働環境、給与の次に大切なのが、仕事に対する遣り甲斐や、その業界・企業の将来性です。休みが多く給与も一定水準を超えていても、全く遣り甲斐を感じられなければ長続きしない事もありえます。
あなたが毎日働くことで誰かをサポート出来たり、感謝されたり、何かが完成し達成感を得られたりと、そういった事が仕事を通して得られる遣り甲斐になります。
又、今後発展していく可能性の高い業界や、企業には活気があり、そういった所で働いた経験は後のキャリアアップに繋がる可能性も高いと考えられます。反対に業界規模が縮小している分野の企業では活気が感じられないケースもよくあります。
遣り甲斐や将来性という部分も考慮し、就職先を選ぶことをお勧めします。しっかり優先順位を付けて後悔しない就職先選びを
就職先を選ぶ上で、いくつかの考慮すべき条件をご紹介しました。新卒で就職した企業は、今後の人生における大切なキャリアになります。今後のライフプランも加味して自分の中で優先順位を決め、各項目における「譲れない基準」と「出来ればクリアしたいが妥協してもよい基準」を其々考えておきましょう。
「とりあえず内定を貰う」「どこでもいいから就職する」という考え方では、内定を得るには、不利になります。将来を具体的に考える力が無いと思われる原因になる為です。
新卒で就職した大学生のうち三分の一程度が三年以内に退職に踏み切っているというデータもあります。しっかりとキャリアを積んでいけるように、具体的な条件も見ながら就職先を選びましょう。 -
新卒時の就職先は?
就職活動を経験した方たちは、新卒時にどんな基準で企業を選んだのでしょうか。会社を選ぶ基準に、給与・事業内容・勤務地・福利厚生・社風・企業のネームバリュー等と、様々な項目があります。余り自分の希望と離れた会社に入ってしまうと、仕事を続ける事が難しくなってしまうかもしれません。
厚生労働省の「学歴別卒業後三年以内離職率の推移」によると、大卒の新卒採用者の内、早期離職は31.9%になるそうです。入社して後悔しない為にも、就職活動をする際は、重視する点を決めておきましょう。就活経験者が新卒時に、企業への応募を決めた理由についてのアンケート調査結果を通してご紹介します。会社を選ぶ際の参考にしてみてください。一位 会社の事業内容 38%
>大学院の修士課程まで行ったので、六年間勉強した専門知識を活かせる業界、大きな仕事が出来るであろう関東での就職を希望していました。夢や期待、やってやろうと言う気概にあふれていた時期でした。[40代 男性/茨城県]
>印刷関係の専門学校だったので、やはりそういった方面に就職しました。[50代 女性/神奈川県]
>やはり、自分がこれからやっていく仕事なので、やりたい仕事をさせてくれる会社であるのが大事でした。 [40代 女性/兵庫県]
企業を選ぶ際に最も多くの方が重視していたのは事業内容でした。やはり大学や専門学校で学んだ事を就職先で活かしたいと考える方が多くいらっしゃいます。特に専門性の高い分野を学んでいた方は、事業内容を重視する傾向が高まります。
又、遣り甲斐を持って働けるかどうかを基準に選んだ方も多くいらっしゃいました。長く仕事を続ける為にも、自分に合う仕事や、昔から目指していた仕事に就きたいと考える方が多いようです。二位 勤務地 23%
>自宅に近いこと、転勤が無いこと、通勤時間が短い事を重視しました。[30代 女性/京都府]
>学生時代、横浜に住んでいたので、卒業後もそのまま住み続ける事が出来る職場を探しました。[30代 男性/大分県]
>自宅から通える所が良かったので勤務地重視で探しました。[30代 女性/埼玉県]
二番目に重視されていたのが勤務地です。自宅から通える範囲内の会社を選びたいと考える方が多くいらっしゃいました。又、転勤があるかどうかも、勤務地を重視する方には重要なポイントです。現在住んでいる所から離れたくない方は、勤務地や転勤の有無を重視して選びましょう。
通える範囲内でも通勤時間が長いと負担になります。通勤時間の長さで転職する方もいらっしゃるので勤務地は慎重に選びましょう。三位 給与・福利厚生 17%
>アルバイト経験豊富だったので、最終的には福利厚生や給与でモチベーションが変わる事を実感していた為。[30代 女性/愛知県]
>一人暮らしでそれなりに生活費も掛かるので、給与は勿論、住宅手当等がある事は重要なポイントでした。[40代 女性/東京都]
>一人暮らしをするので給与面で問題が無いか、社会保険等の心配が無いように重視しました。[30代男性/新潟県]三位は、給与や福利厚生を重視した、と言う回答です。代表的な福利厚生には、社会保険料の負担・各種手当・健康診断・社員食堂と言ったものがあります。福利厚生の充実した企業だと安定した環境で働けるため、長く仕事を続けやすくなります。
又、給与や住宅手当の有無などは、生活に大きく関わります。生活費を考慮し、十分な給与が出る事を基準に企業を選ぶ方もいらっしゃいました。特に一人暮らしの方は給与や各種手当を重視する場合が多いようです。まとめ
アンケートの結果、新卒時に最も多くの方が重視したのは、事業内容と言うことが分かりました。長く働き続ける為、遣り甲斐の有る仕事をしたいと考える方が多くいらっしゃいます。又、大学や専門学校で学んだ事を活かせる所で働きたいと言う意見も多数ありました。
次に多かったのは、勤務地を重視すると言う意見です。自宅から通える範囲内に就職したいと言う方が多くいらっしゃいました。入社後は環境がかなり変わるため、住居も変わるとなると大きなストレスになる可能性があります。現在住んでいる所を離れたくない場合は、勤務地を考慮して会社を選びましょう。尚、転勤の有無にもお気をつけ下さい。
また、給与や福利厚生を重視する方もいらっしゃいました。給与額や福利厚生の充実度は、生活を大きく左右します。福利厚生には、保険加入・住宅手当・オフィス内食堂などと言った物が有り、生活費を抑えられたりいざと言う時の保障があったりする物に人気が集まります。他にも、休憩スペースの設置やスキルアップの為の研修、シェスタ制度と言ったように様々な福利厚生があります、企業に応募する際は福利厚生の内容に注意してみてください。
又、女性の場合は、長く働き続けるためには、産休・育休制度の整っている会社に勤める事も重要です。この制度が整っていないと、本人に仕事を続ける意志が有っても、妊娠後に退職せざるを得なくなってしまう事もあります。
社員の退職理由で多いのは、人間関係・労働時間・職場環境・仕事内容・給与・社風などと言ったものです。人間関係は入社前には分かりませんが、その他の項目はある程度は調べられます。重視する点を決めて会社を選ぶことにより、入社語のミスマッチを防げます。
これから就職活動をする方は、ぜひこのアンケートで上位になった「事業内容」「勤務地」「給与・福利厚生」と言った条件を確認しながら企業を選んでみてください。 -
激化する就活戦線、エントリーした企業の数
最近は「就職氷河期」と呼ばれた時期も過ぎ、就職活動は学生有利な「売り手市場」になったと言われています。確かに全盛期の頃と比べると、エントリーした企業数の平均値自体は下がっているようです。しかし、中には新卒採用におけるエントリー数が数十社にものぼる方もいる事から、氷河期が過ぎたとはいえ就活戦線は依然として厳しい状況下にあると言えるでしょう。
就職活動が出来る時期が短縮され、時間が限られるようになった今、どれくらいの数の企業にエントリーしておくと良いのでしょうか?ここで、これから就職活動を始める学生さん達に向けて、新卒採用を経験した先輩達がエントリーした企業の数をご紹介します。先輩達がどのような理由でどの位の数のエントリーをしていたのか、集まった体験談を参考にしてみてください。新卒の就活時、選考にエントリーした企業数は?
一位 五社以下 56%
>技術職の就活でした。大学経由の推薦枠が充実していたので多数エントリーする必要はありませんでした。[30代 男性/千葉県]
>公務員試験を受けたので自宅通勤可能な近辺の市しか受けなった。[20代 女性/愛知県]
>バブル期だったので今の様に多数応募すると言うより、絞り込んで応募するイメージだった[50代 女性/東京都]五社以下と少数のエントリーで済ませた方の中には、専門職や公務員といったやや特殊な職種であるため、それ程多く応募する必要が無かったと言う声が見られました。又、その一方で世代によっては現在の新卒採用とは仕組みが異なるため、多数のエントリーを行う必要が無かったようです。志望する職種や業界によっては、必ずしも多数エントリーするとは限りません。ご自身の進路によっては五社以下で就職先が決まることも十分に考えられます。
二位 六~十社 17%
>行きたい企業に絞ってエントリーしたので他の人よりは少なかった。[20代 男性/千葉県]
>就職活動を甘く見ていて、余り必死にエントリーしませんでした。自分の条件に少しでも合わない所はエントリーしなかったので、後々苦労しました。[30代 女性/神奈川県]
>本当に自分が働きたい会社にのみエントリーしました。[20代 女性/東京都]志望企業を絞り込み、六~十社に留まったという声も多く集まりました。ひとまず多数の企業にエントリーして、どこかの内定を狙うとよりも、本当に行きたい企業を厳選して就職活動をしたと言う方の意見が目立ちました。但し、中にはエントリー数が少なすぎて中々内定が獲得できずに後悔した、と言うコメントも・・・。就職活動は終盤に近づくにつれてエントリーできる企業の数も減ってくるため、万が一の事態も考慮しつつ計画的に進めましょう。
三位 二十一~五十社 12%
>出来るだけ多くの企業にエントリーして、不安を解消したかったから。[20代 女性/青森県]
>エントリー自体には余り手間が掛からないので、多目に申し込んでしまいました。[20代 女性/滋賀県]
>就職氷河期時代だったので、内定を勝ち取るのも一苦労でした。業界を絞らずに活動していました。[30代 男性/大分県]就職活動は何が起こるか分からない物です。内定を一社も獲得できないリスクを避ける為、あえて多めにエントリーした、と言う先輩もいるようです。企業へのエントリーは学生にとって、それ程手間の掛かるものでもありません。その為、保険の意味合いでやや多めに応募したと言う意見も見られました。又、就職氷河期に新卒採用を経験した方は、業界や職種を絞らずに出来るだけ多くのエントリーをした為にこのような結果になったようです。
まとめ
このアンケート調査では、就職活動でエントリーした数が五社以下の方が大半を占めており、これに続き六~十社、さらに二十一~五十社エントリーしたと言う結果でした。但し五社以下と回答した方の中には、好景気の時に就職活動した世代の方や、公務員、専門職など特殊な職業を希望した方も含まれます。必要以上に多数のエントリーをしなくても大丈夫ですが、少なくとも二十社程度はエントリーする心構えでいたほうが良いでしょう。
ここの所、新卒採用は学生が有利な“売り手市場”と言われています。かつての就職氷河期では、五十社以上のエントリーをする学生もいました。現在はエントリー数の平均値も下がりつつあり、自分の行きたい業界や就きたい職業を厳選する学生が増えて来た様です。しかし売り手市場とはいえ、内定を獲得できるかどうかはやはり本人の努力次第といえます。リスクヘッジの為にも、まだエントリーできる時期のうちに応募しておくのも手段の一つです。
比較的多くの企業にエントリーすると、スケジュール管理が困難になる他、就職活動に掛かる時間が大幅に増えてしまうと言ったデメリットがあります。しかし多くの企業にエントリーするからこそ、得られるメリットもあります。たとえば、あえて業界を絞らずにエントリーする事で、就職先を絞り込む際に広い視野を持てるのは大きなメリットと言えます。まだ志望業界や職種が定まっていない内なら、エントリーを多くすることで多数の選択肢に恵まれるかもしれません。
その反面、エントリー数を絞り込んで就職活動を行うと、企業や業界を研究しやすいと言うメリットがあります。志望する業界や職種によっては、少数のエントリーで十分な可能性も考えられます。今後の就職活動において、ご自身の志望進路の傾向に合わせてエントリー数を検討しましょう。 -
グループディスカッションの役割毎の特徴
グループディスカッションでよい評価を得る為には、其々の役割ごとの特徴を見極め、結果に繋がるよう有意義なディスカッションを行うことです。
就職面接でよくある質問は、様々な書類に目を通せばある程度予想できます。代表的な質問に対する答えはあらかじめ用意できますから、それ程答えに困る場面は無いでしょう。
しかし、複数の人間を相手に会話をするグループディスカッションは、多種多様なテーマを設定される可能性があり、シミュレーション通りに議事が進むことはありません。実際の業務の中で発生しうる多様な状況に対応する能力を見る為、現在では多くの企業が選考にグループディスカッションを取り入れています。
グループディスカッションでより良い評価を得るため、役割に応じた議事の進行をする必要があります。其々の役割ごとの特徴を把握し、結果に繋がるよう有意義なディスカッションを行いましょう。議論の「司会」進行役
グループディスカッションでは最初の話し合いやくじ引き等で、参加者の中の役割を設定するケースが良く有ります。役割分担で必ず決めなければいけないのが進行役の「司会」です。
グループディスカッションの中で最も話す機会が多いので、上手くこなせれば評価を得やすいポジションとなります。その為積極的に立候補し、自ら司会役を買って出る人もいます。しかし逆に議論がうまく盛り上がらなければ逆に評価を落としてしまう可能性もあるので注意が必要です。
司会として評価を得る為に大切な事は議論が盛り上がるためのサポートです。全体を把握し、時に指名を交えながら参加者から意見を引き出しましょう。都度、意見を整理して、書記が纏め易くする事も大切です。議論の記録役「書記」
ディスカッションの中で出てくる意見や、進行の内容を記録して行く係です。単純に交わされた意見を羅列していくだけでは、後の発表の際に困りますが、意見を端的に纏めて分かりやすくしたり、立場毎に整理しておくといった工夫をすれば、発表者の手助けになります。
目立つ役割ではありませんが、工夫して記録を残していけば確実に評価されます。
但し、記録する事だけに集中してしまい、議論の傍観者とならない様に注意も必要です。グループディスカッションは、参加者全員が自分の意見を明確にして話し合う場です。どれだけ綺麗にノートを纏めても、議論に参加していなければ評価は得られません。
意見を言わ無くても、仕事はしていると言う印象を得られると考え、人前で意見を言う事が苦手な大人しい人が、書記をしたがる傾向があります。全体を把握しつつ、自分の意見の発表もしなければならないため、複数の事項を同時に処理できる能力に自信のある人にお勧めします。議論の管理役「タイムキーパー」
グループディスカッションでは、正解が決まっていない議題が設定されます。参加者其々が、自分の意見を主張して盛り上がりすぎてしまうと制限時間内に意見を纏められません。
タイムキーパーは「各自が自分の意見を自由に出す」「自分の意見のメリットを主張したり、他の意見の問題点を指摘したりして話し合う」「議論で出たグループ内の意見を纏める」と言ったように、制限時間を幾つかのセクションに区切る役割です。
司会や書記と違い、タイムキーパーは設定しない場合も有ります。予め決められていないケースでは、立候補してもいいと思いますが、タイムキーパーも自分の意見を発表する必要があることをお忘れなく。その他のポジション
グループディスカッションに何度も参加していると司会や書記、タイムキーパーといった役割を与えられないケースも良くあります。その場合は逆に議論の内容に集中するチャンスと捕らえましょう。ディスカッションでは自分の意見を発表するだけでなく、なぜそう考えるに至ったか、その意見のメリットは何か等を端的に纏めて人に伝える必要があります。自分の意見を言わない人は論外ですが、ダラダラと長く話していても良い評価は得られません。
又、反対意見に立つ人に対しても、共感や理解を示す姿勢が大切です。実際に仕事の現場では、意見が対立したからと言ってケンカ腰で対処する訳には行きません。相手の意見の良い所は認めつつ、問題点や疑問点をひとつずつ解決していきましょう。グループディスカッションで見られているポイント
グループディスカッションは、自分の意見を押し通せば勝ち、相手の意見に賛成すれば負け、と言う勝負ではありません、納得出来るなら意見を曲げることが有ってもよいのです。議論の盛り上がりに貢献している事が高い評価になります。
司会や書記、タイムキーパーの役割についた場合、其々の仕事をキチンと果たしながら自分の意見も出していく事も大切です。それを意識して、建設的な議論を積極的に交わしましょう。 -
就活中に気を付けるべき身嗜みのポイント
就職活動時の「身嗜み」と言うと、髪型やメイクの仕方、服装などをイメージする人が多いかも知れません。しかし、身嗜みが意味する所は他にもあります。かばんや靴等スーツ以外にも身に付ける物はありますし、アクセサリーや香水なども含まれます。これらを「どのように身に付けるか」と言う事を考える必要があります。又、コートのように、季節によっては必要となる上着の扱いも就活時の身嗜みに含まれます。
ここでは、そうした就活時に必要なアイテムや装身具の身に付け方ついての注意点をご紹介します。1 かばん
就活時に使用するかばんは、多くの場合就職後も継続して使用する、ビジネスバッグを兼ねる事になるはずです。注意点として、派手な色合いの物や、奇抜なデザインの物は避けましょう。地味な物を選ぶ必要はありませんが、ビジネスに適した機能的なかばんを選ぶと良いでしょう。
選び方のポイントは「スーツに合う物を選ぶ」事です。基本的にビジネスに必要なアイテムは服装とセットでチェックされる為面接時などに着用するスーツと合わせたときに違和感の無いものを選べば問題は無いと言えます。2 靴・靴下
靴に関して、男性の場合はスーツに合う黒色系の革靴がお勧めです。面接等晴れの場で使用するのですから、ピカピカに磨いておいた方が良いのは言うまでもありません。汚れや傷が目立ったり、靴底が磨り減っているのが分かるような靴を履いたりするのはNGです。
革靴にも幾つか種類がありますが、就活時には標準的なプレーントゥのシューズが適しています。つま先が尖っている等、奇抜な形をした靴は、足元に余計な注意を引き付けてしまう恐れがある為使用は控えたほうが良いでしょう。
靴下も靴やスーツと合うよう黒系の、くるぶしがしっかり隠れるものを選びましょう。くるぶしが露出するタイプや、白い靴下等は、椅子に座った時に外から見えてしまい、奇抜なデザインの靴同様、足元に視線を集めてしまう恐れがある為、避けた方が無難です。
女性の場合は、靴はやはり黒系のパンプスを選ぶのが良いでしょう。ヒールは3~5cm程度の物が疲れにくく、足元も綺麗に見えます。就活時は様々な企業を行き来する事になりますので、見た目の美しさばかりではなく機能性も考慮して靴を選びましょう。
ストッキングはナチュラルカラーと呼ばれる、自分の肌色に近い自然な色合いの物を選び、途中で伝線してしまった時等に備え、予備を用意しておきましょう。3 アクセサリーや香水
アクセサリーも身嗜みの一部なので、服装と合っていれば身に付けても大丈夫です。男性なら指輪、女性なら指輪やネックレス、ピアスなどが該当します。エンゲージリングや結婚指輪を始めとして、過度な装飾が施されていないシンプルなデザインのアクセサリーは身に付けても構いません。但し、サイズ自体が大きい物や動いた時に音が出るような物は面接の妨げになりかねないので、使用しない様にしましょう。
香水については、体臭を抑える等の役割もありますので使用しても構いません。但し香りのきつい物は周囲の人に刺激を与えてしまう恐れがあるので、使用量に注意してあくまでも「ほのかに香る」程度に留めておきましょう。4 コート
寒い季節の就活には防寒具として、コートが必要になると思います。靴と同様に、スーツと合わせる事が基本ですので、スーツに合うデザイン・色合いの物を着用するようにしましょう。コートで特に気を付けたいのが、取り扱い方です。企業を訪れた際は建物内に入る前に脱ぎ、二つ折りにして腕に掛けた状態で入場しましょう。面接時の正装はあくまでもスーツであり、コートは防寒具に過ぎないと言う事を忘れてはいけません。マフラーや手袋等、その他の防寒具についても同様です。
「花粉症」などで症状を抑えるためにマスクをしている場合でも、建物内に入る前には外しておいた方が無難でしょう。もし症状がきつく、外すのが難しいようなら、始めに企業側担当者に事情を説明し、許可を得た上で着用するようにしてください。事前に身嗜みについて知っておき、準備を怠り無く!
就活時の身嗜みはそのままビジネスマナーに繋がる事が多いため、覚えておくと就活時だけでなく修飾語も役立つことが多いのです。何も知らずに面接の場で恥をかいたり、知らず知らずのうちにマイナスの印象を与えてしまったりする事が無いよう、就活を始める前に良く確認しておいて下さい。
かばんやコート、靴等、どのような物を選んだら良いか、自分だけでは判断が難しいようなら、販売店の店員に「就活用の物を選びたい」と事情を説明して、アドバイスしてもらうのも良いでしょう。
実際に面接時に着用するスーツで店舗を訪れれば、試着して着こなしを自分の目で確かめることも出来ます。一人でチェックする自信が無い場合など試してみてください。 -
就活生の誰もが抱く就活スタート時の悩み解消法
就活生にとって人生の分岐点である就職活動では、企業へのエントリーや面接の対応等はネットなどを検索すればすぐに分かりますが、ご自身の内容や悩みは検索しても中々答えが見つからない物です。 就活生からお聞きした悩み事を集め、誰もが抱くであろう就活スタート時の悩みを、キャリアコンサルタントで現在は国立理系大学キャリアセンターでアドバイスされている『川楠 裕子』先生に、やりたい事が見つからない、企業の情報収集の仕方、自己アピールの決め方、の三大悩みの解消法についてお話をうかがいましたのでご紹介いたします。
キャリアコンサルタント就活支援アドバイザー
川楠 裕子 先生
・2級キャリア・コンサルティング技能士
・国家資格キャリアコンサルタント
・産業カウンセラー
私立大学・国立理系大学のキャリアセンター(就職支援室)での講師ならびに相談業務を始め、企業内カウンセリング室における定期カウンセリング、またキャリアコンサルタント養成講座、行政、企業などの研修講師として多岐にわたり、再就職支援、大学の就職支援室など幅広く相談業務に携わる。管理職、両立経験を生かした企業内カウンセリングを得意とする。IT企業を長く担当し活動中。
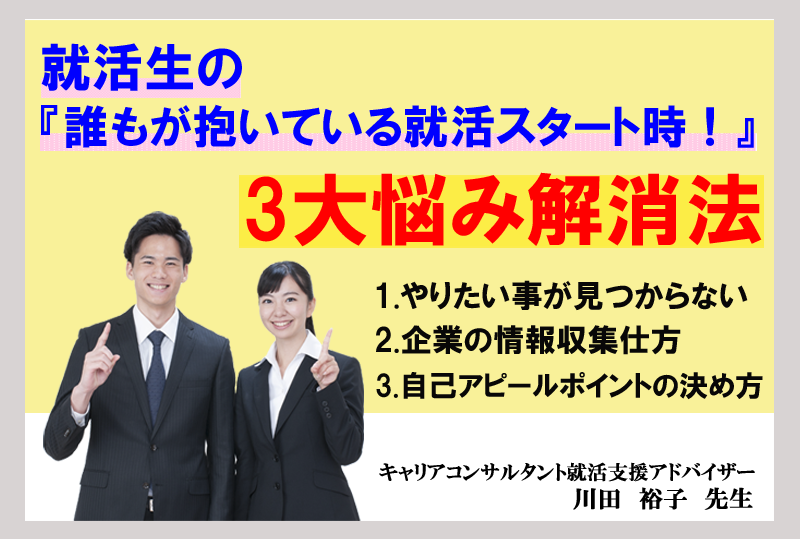
Q、将来の方向性や、やりたい事がまだ見つからない時はどうしたらよいでしょうか?
「やりたいことがわからない」と相談に来られる学生さんは多くいらっしゃいます。
実はこれ、社会人の方からも「よくある」相談なんです。「転職したい、でもやりたいことがわからない」といった相談です。
そして、バリバリ働きながらも「やりたいこと探し」をしている人はたくさんいます。
今の仕事を頑張ることでやりたいことが見えた、異動した際に前の仕事がやりたい仕事だったと気づいた、と色々です。
実は私は「今、やりたいことが無い」のは構わないとさえ思っています。しかし、「無い」「わからない」ことで、途方にくれてしまって動けず、立ち止まってしまう人がいます。
これは勿体無いですね。分からないからこそ、動いてみる、色々な経験をすることをおススメします。
たとえば、OB/OG訪問、インターンに行ってみる、会社説明会などのナマの情報収集はどうでしょうか?活字とは違った刺激もあることでしょう。
また、大学の先輩たちがどんな会社に行ったのか調べてみる(自分と同じ専攻・学びをした先輩の興味とは通じるかもしれません)などもリアリティがあります。
やりたいこと・興味は、「知らない」ところからは生まれてきません。どんな業界が在って、どんな仕事があるのか、先ずは大きいところからでも情報を得てみませんか?そしてそれらを知ったとき、面白そう、とか興味のアンテナが立ったとき、どうして自分がそこに惹かれたのか、考えてみましょう。
そこに自分の今までの経験などから通じる物があるかもしれません。たとえ経験に通じていなくても、その理由が見えてくると、ESや面接の言語化にも役立ちますし、方向性が絞れてきます。
やりたいことの「正解」探しをしてしまうことで、自分を拘束してしまい、却って動けなくなってしまう人がいます。
まずは動いてみましょう。どうしても動けない、一歩が踏み出せないという方は、大学のキャリアセンターなどの相談を使って下さい。
「何をしたらよいか分からない」と来られる学生さん、どこのキャリアセンターも大歓迎ですよ。Q、業界や企業の情報収集はどのようにしたら良いですか?
情報化社会と言われていますので、情報は様々なところから得ることが出来ます。
まずは就活サイト。最近は大学名を登録すると、同じ大学の人がよく見ている会社とかそんな切り口からも調べることが出来ます。
そして活字・本です。会社四季報・就職四季報、業界地図や仕事図鑑など。また、新聞やテレビなどからも話題の商品とかサービスなども触れることが出来ますね。
また、前述しましたが大学のキャリアセンターなども情報の宝庫です。生の情報としてインターンや会社説明会は欠かせません。
大学でのOB・OG説明会、OB・OG訪問も有効活用したいものです。企業の情報収集としてHPは必須ですが、IR情報を見ていない学生さんが多いです。
投資家向けの情報ですが、企業の財務・経営状況を知ることが出来、客観性のある情報として価値があります。そこには企業の課題や今後の方針なども記載されており大変興味深い内容となっています。ぜひ活用してください。Q,自己分析、アピールポイントが自分ではわからない場合はどうしたらよいでしょうか?
周囲の人に聞いてみるのも手です。「ジョハリの窓」という心理学で学ぶ手法ですが、自分が知っている自分だけが自分ではない、他人から見える自分も自分である、という視点です。
新しい自分が発見でき、自己理解がさらに深まるといわれています。また、自分の事って、なかなか客観視できません。
自己分析の中で、色々なエピソードを学生さんに聞かせていただくと「たいしたエピソードではない」「こんなことは誰でも出来る」という方が本当に多いです。
そのため具体的なエピソードが無い、強みが無いという風になってしまいます。他人と比べるのではないのです。
人事の方も「エピソードコンテストするつもりは無い」と話されています。とは言え、自分ひとりで苦労されている方は、キャリアコンサルタントを活用して欲しいと思います。
大学のキャリアセンターにいる相談員でこの資格を取得している人が多くいます。学生時代のエピソードを聞かせていただきながら、色々とご質問させていただく中で、その方の思いや考え方、興味、価値観、強みなどを一緒に探っていくお手伝いをします。
先日も、私が「なんで?」を連発して聞いていたら「チコちゃんじゃないけど・・」とついつい言ってしまい、お互い爆笑してしまいました。こんな風に和やかにやっています。
気軽に相談してみてはいかがでしょうか?就活は正解が無い事で、苦しさを感じる方も多くいらっしゃいます。一人で抱え込まないこと、専門家の活用は乗り切るための常套手段です。今回、就活スタート時の三つの悩みとして川楠先生に伺いました内容です。
川楠先生貴重なご意見有難うございました。
人生の分岐点で悩み、迷い、そこからご自身で選んだ方向に進めるよう就活生を応援し続けます。 -
インターンシップはいつから?
インターシップとは社会に出る前に体験通じておくことで仕事や業界など社会への理解を深め、より納得のいく企業選びに繋げることを目的に行います。
毎年インターンシップに参加する就活生は、60%程と言われており、インターンシップの参加者数は平均4.5社とされています。インターンシップの実施期間は、企業により様々です。
三日以下の予定をしているインターンシップに参加する就活生は約七割。
希望の業界に決まっていない就活生は色々な業界や企業を見る為に、短期のインターンシップに多数参加し、その他、四~七日間は約二割とされています。ある程度希望の業界に絞れている就活生は、長期のインターンシップに参加しているようです。インターンシップの内容は、企業や業界により異なりますが、基本的に仕事の体験ですので業務遂行が含まれていたり、プロジェクトを組んだり、グループを組み、会社の一員として行われます。
インターンシップの時期は、八月が最も参加が多く、就活生の夏休みに合わせて企業側が参加しやすくしている事も有ると思われます。又、次の年のエントリーが始まる三月目の二月も多く行われ、早くから就活を始める学生が八月に行う傾向と見られます。
ピークは八月と二月です。
インターンシップへの参加にあたり、準備があると思います。参加人数の制限が有る場合や、面接等がある場合も有ります。マイナビ、リクナビや気になる企業のHP、学校のキャリアセンターなどで確認し、必要に応じて準備をしていきましょう。
色々な情報を人よりも多く取り入れる事で、上手く行くケースも有ります。
情報とは知識を得ること。知識が付けば様々な考え方を選択できます。より良い就活になるように、情報を得ることをお勧めします。 -
まとめ
今回は、すでに就活をしている学生に一度通ってきた道を振り返ってどのように感じるのか、又、これから就活を始める学生にはまだ通った事の無い道を見てもらい、感じてもらうことにより、新たな考えを持ち、成功(内定)へ近づいてもらえたらと思い、応援しております。
少しでも就活生の力になれましたら幸いです。